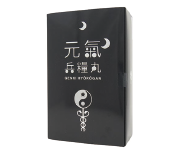およそ10人に1人
「産後うつ」というと、母親のことを思い浮かべます。でも実は父親にも起こることが知られています。日本でも、2020年に国内初のメタ解析がおこなわれ、妊娠期は8.5%、産後は8.2~13.2%と時期ごとにばらつきはありますが、妊娠期から産後1年にかけて、およそ10人に1人の父親がうつ症状を抱えることがわかりました。特に産後3〜6か月の時期はリスクが高いそうです。予想よりも高い割合だと思いませんか?
妊娠期が調査対象に入っていることからもわかるように、「産後」と名前がついていても、妊娠中からその兆しはあるそうです。母親が体調や気持ちの変化に揺れるのと同じように、父親も心身が変化していきます。
あまり知られていませんが、男性もパートナーの出産前後にホルモンバランスが変化するんだそうです。女性は分娩や授乳を促進するオキシトシン(愛情ホルモンといわれます)が増える一方、男性はパートナーが出産を迎えるとき、テストステロン(男性ホルモン)の値が下がるんですって。つまり、母親ばかりでなく父親も、赤ちゃんとの絆を深めやすいモードに、自然と体がシフトしていくわけです。父親のホルモンバランスが変わることで、攻撃性が抑えられ、赤ちゃんに関心を向けやすくなります。赤ちゃんを抱っこしたり、おむつ替えをしたり、育児に関わることを通して、男性のホルモンの働きが安定し、バランスが整う後押しになります。逆に、育児から離れてしまうと、その変化が活かされず、心の疲れがたまりやすいという報告もあります。
「ホルモンのせい」だと知る
一方、パートナーの妊娠・出産時の父親のテストステロンの低下の度合いによっては、気力の減退や抑うつ症状につながることがあるそうです。他には、出産のころにはストレスホルモンのコルチゾールが一時的に上昇し、父親も泣き声などの刺激に敏感になるそう。一般に母親ほどではないと、母親からの嘆きも聞きますが、父親も赤ちゃんの声で目を覚ましやすくなっているはず。母親の場合は、妊娠中から授乳に備えてちょこちょこ目が覚めるようになるなどの知識は得やすいですが、父親も敏感になることは、あまり知られていないと思います。すると、父親が眠りづらいのは、ホルモンバランスの影響ではなく、純粋に赤ちゃんのせいになってしまいかねません。
睡眠不足が続いたり、仕事のために育児参加が限られたりすると、父親のホルモンバランスは崩れやすくなり、結果として産後うつのリスクも高まります。逆に赤ちゃんとのふれあいを積極的に楽しめる父親だと、オキシトシンが多く分泌され、幸福感や安定感のもとになる。ホルモンの助けを借りて親になり、さらに守られるわけです。そういう動物としてのバランスの知識が、母親より父親に関して、足りない傾向があるのではと思います。
「パパの産休」制度ができるなど、父親が家事や育児を「手伝う」のではなく「担う」方向へと制度が整い始める一方で、社会的な支援や職場環境が追いついていないといった理由で、悩みを抱えるケースもあると思います。
父親がメンタルヘルスの問題を抱えると、母親の心身の回復や赤ちゃんの健やかな成長にも影響があるといわれます。産前・産後を通して家族で無理なく支え合えるよう、妊娠中からお互いに話し合っておけるといいですね。