もはや市民権を得た「マクロビオティック」。その創始者は、海外で〝ジョージ・オーサワ〟の愛称で知られる、櫻澤如一氏です。「食物の陰と陽」「一物全体(食材を丸ごと使用する)」「身土不二(その土地のものを食べて生活する)」などのマクロビオティックの教え。そこには櫻澤氏が、食を通して伝えようとした人間の正義が存在します。もとは「食養」と呼ばれる、マクロビオティック。その真髄を、櫻澤如一研究家・安藤泰弘氏に聞きました。

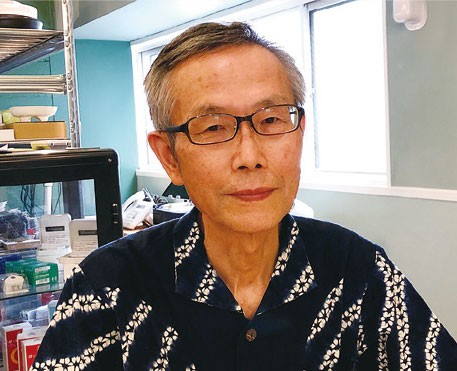 櫻澤如一研究家
櫻澤如一研究家
安藤 泰弘(あんどう やすひろ)
1949年、神奈川県平塚市生まれ。大学生のときに櫻澤如一氏の教えに触れ、マクロビオティックに開眼する。そのまま学校を中退して、パートナーで櫻澤流新普茶料理師範のゆりさんとともに新潟県に移住、豪雪地帯での自然農耕を実践する。30年間の新潟生活の後は沖縄に移住し、現在は生まれ故郷の平塚在住。日本だけでなくベトナムで、櫻澤如一氏の食養の教えの普及に努めている。
食養の教えの足元にある東洋の思想に興味を抱いて
――安藤さんは海を越えて、ベトナムでも櫻澤如一氏(1893~1966年)が創始したマクロビオティックの普及に努めておられます。「食養」とも呼ばれる、マクロビオティックに興味を持ったきっかけを教えてください。
学生の頃に、慢性気管支炎を患っていました。日常的に通院して、医者に薬を処方してもらっていましたが、あるとき、大学の先輩が「これを読んでみたら?」と2冊の本を貸してくれたんです。それが櫻澤先生の著書『新食養療法―マクロビオティック 健康と幸福への道』と、『東洋医学の哲学―最高判断力の書』でした。先輩はこの本の教えを実践して、持病が治ったというのです。
私も目を通し、思わず「面白い!」と唸ってしまいました。そのときはマクロビオティックのノウハウよりも、櫻澤先生が綴った東洋の思想に夢中になってしまったのです。
戦後日本の6・3の義務教育と高校3年間、また大学に進んでも、多くの人が履修するのは西洋の学問。私も大学生になるまでは、仏教の教義や老子の思想などに深く触れて、熟考したことはありませんでした。だから本に書いてあることすべてが、新鮮に映りました。
もちろんマクロビオティックの教えは、「陰」と「陽」の食品をバランスよく摂ることを挙げても、その根底に東洋の医学や哲学が流れています。そして、それらの根拠となっているのが、儒教の経典のひとつ『易経』や、中国で春秋時代に書かれた『老子道徳経』です。
櫻澤先生の著書に出会って、私はそのバックボーンたる東洋思想に傾倒していきます。当初は『東洋医学の哲学』の影響をより強く受けていました。
それは当時の私が、西洋科学の限界を感じていたからです。私が学生時代を過ごしたのは、1970年前後の東京。街のあちこちで工事音が鳴り響いていて、空気にも淀みを感じました。また水質汚濁や土壌汚染、地盤沈下などの公害で、日本各地から悲痛な叫びが起こっていた時期でもありました。すべては科学、西洋のケミストリーで経済の合理性を追求した結果、引き起こされた惨劇なのです。
私はこの現状に危機感を抱いていました。だからこそ櫻澤先生が説く東洋の思想が、スムーズに頭と身体に入ってきたのです。また櫻澤先生も、自著で西洋科学を覆し、東洋の思想で世を改めることを説いておられました。
一方でマクロビオティック、私は「食養」の呼称の方を好んで使いますが、これも実践してみました。まず玄米を主食にしましたが、これは白米よりおいしく感じて、難なくクリア。しかし苦労したのが、砂糖を抜くことです。
食養においては、白砂糖は「極陰」とされ、とくに身体を冷やすとされます。しかし当時の私は、大の甘党。ごはんにも、白砂糖をかけて食べていたくらいです。また病弱で小さいときから医者に通っていましたが、薬を服用するときには、苦さを紛らわすために砂糖水で飲んでいました。くわえて、甘い菓子にも目がなかったので、一気に砂糖の摂取をやめると、禁断症状が出たのです。
実際には、食生活から砂糖を抜くことにかなり苦労しましたが、それでも曲がりなりにも食養を実践していると、気管支炎がいつの間にか治ってくれたのは、ありがたいことでした。
食養に導かれて移り住んだ
新潟で体感した、理想の暮らし
――ちなみに大学を出た後は、どんな選択をされたのでしょう?
いえ、大学は中退してしまったんです。これも櫻澤先生の著書『永遠の少年 ―健康と幸福への道』(1952年刊行)に触れて決断したことです。思い切って大学を辞め、ここに書かれたことを実践すべしと、心を揺さぶれたのです。
この本には、家庭の事情で13歳で社会の荒波に投げ出され、その後に病弱と貧乏のどん底から這い上がった櫻澤先生の50年に及ぶ人生の叡智が詰まっています。『永遠の少年』が発刊された当時は、戦後の混乱の最中。櫻澤先生がそうだったように、雨の日も風の日も働く十代の少年少女に向けた人生の指南書が、この本でした。
先生は、最終章において、人間が幸福な一生を送るためには、「強い記憶力」「正確な判断力」「大胆な実行力」が必要と説いています。そしてそれらを育む第一歩として、玄米や分づき米、雑穀を主食として、お茶少々でよく噛む食生活を勧めています。家庭環境に恵まれないために、学歴を積めなかったものの、自身の努力で多言語を操って、世界に食養を普及させた櫻澤先生。その先生が言うからこそ、生きるうえで、いかに食養が大切かが伝わってきました。
――大学を辞めた後、どのようにして櫻澤流の食養を極めようと考えたのでしょうか?
新潟県新井市(現在の妙高市)の山奥へ移住しました。将来的にはガソリンとは無縁の生活を送りたくて、木曽馬という在来馬を飼って田畑を耕す、自然農法を実践してみたのです。しかし「牛飲馬食」という四字熟語があるように、馬はとにかく大量に餌を食べます。農作物を作る前に、まずは飼料用の茅や稲わらを確保するのが大変でした。馬を一頭飼うことの意味を知ります。
また新井市のある新潟県上越地方は豪雪地帯なので、夏、いや春のうちから、冬の準備をしておかねばなりません。夏には、私たちの食料を育てながら、一冬ぶんの馬の飼料を確保すべく、農道に茅を大量に広げて乾燥させました。その香りが、なんとも自然の力を感じる匂いで、自分がいま、ここで生きているという実感が湧いてきます。
しばらく自然農法に没頭しましたが、やがて子どもを授かります。今度は同じ新潟県内の十日町市に引っ越して、生計を立てるべく、パートナー(櫻澤流新普茶料理師範・安藤ゆりさん)は、自然食品や自然雑貨の店を開業しました。私は気の治療をしながら、食養の相談にものっていました。結局、30年間、新潟で暮らしました。
私たちの家は山村にあったため、ご近所はお百姓さんばかりでした。ここにいれば、自ずと先人が、いかに暮らしていたかが見えてきます。
隣には、私の父親と同じ年のおじいさんが住んでいました。彼の毎日の仕事は、畦道の草刈りから始まります。来る日も来る日も、飽きずに側道の除草に勤しむのです。刈った草は毎日、息子さんが回収して堆肥にします。
農家の夏休みは2日間、お盆の8月15日と16日。またその日には、仏壇に自分で育てた盛りの花を供えます。「この質実な暮らし方こそ理想だ」。私は村の人たちを見ながら、心からそう思いました。
江戸時代の医師で、思想家でもあった安藤昌益(1703~1762年)は、すべての男女が労働(男は耕し、女は織る)に励むべきという説を、自著『自然真営道』で説いています。彼の理想の生き方は「直耕直織」の四文字で表現され、その「衣と食」の製産という人類普遍の生き方に、私は以前から惹かれていました。
そして私と同じように、在りし日の櫻澤先生も安藤昌益の理想に共感されていたようです。狩野亨吉(1865~1942年)が昌益を発掘した著作『安藤昌益と自然真営道』を、先生が100部復刻して広めたのです。
櫻澤先生の教えに「つつましやかに生きよ」があります。そこには、安藤昌益の理想と通ずる部分があるのです。
自分の人生だけではなく、
全人類に正義をもたらす食養
――「つつましやかに生きよ」とは、どのような生き方なのでしょう?
まず食生活において、つつましやかに生きるということです。
官僚で民俗学者だった柳田國男(1875~1962年)が見出した、日本人の時間の感覚を表す言葉に、「ハレとケ」があります。ハレ(晴れ)は慶事などの非日常、ケ(褻)は「日常」を指します。
櫻澤先生が大切にしたのは、ハレではなく、ケの日の食事のつつましやかさ。主食(穀物とそれに準ずる、そばなどの種子類)を「3」としたら、副食は「1」の比率としました。日本の伝統的な食法です。病気を治したければ、主食「5」にお菜「1」ですが、ベトナムでは3:1の食法で重い病気がよくなったという報告も来ています。これは、ベトナムも原産地のひとつといわれる、お米(玄米)の場合です。日本もお米の栽培に適した風土ですから、桜澤先生も〝玄米単味〟を若い頃主張しているくらいです。
「和食の基本は一汁三菜」と言われますが、「一汁一菜」が理想的だと思います。最近では、料理研究家の土井義晴さんが著書『一汁一菜でよいという提案』で、一汁一菜の利点に言及されておられます。一汁一菜は決して手抜きではなく、一品一品に気持ちを込めて作れば、日本人に適った食事のかたちなのです。
日本の歴史に立ち返ってみてください。先祖は、そのほとんどが農業に従事していて、一汁一菜の食生活が中心でした。私が子どもの頃も、朝ご飯といえば納豆と味噌汁で、学校に行けば、よく同級生の歯に青のりが付いていたものです。昔からケの日の一汁一菜が、私たちの身体と精神の健康、日本の社会と文化を作ってきました。このシンプルな食生活の繰り返しこそが、食養の基本です。
そう考えると、いま、世間で持てはやされるマクロビには、食養の概念からかけ離れた料理も散見されます。パフェやパスタ、ちょこちょこと惣菜だけがのったランチプレートなど。いずれも見た目は華やかですが、食養の基本はやはり、ご飯と一汁一菜の組み合わせです。そんな櫻澤先生の食養の根幹を伝えるべく、いまでは日本だけでなく、ベトナムでも、その普及に努めています。
――日本とベトナムを行き来して、食養の指導をされています。
「たとえ流れ弾が当たってもいい」。1965年、食養の教えを広めるべく、戦時中のベトナムへ命がけで渡った櫻澤先生。その教えは、いまや全土に広まって、ベトナムには熱心なマクロビオティックの実践者がたくさんいます。また日本よりも敬虔な仏教徒が多く、毎月1日と15日だけは精進食を口にするという人も。ベトナムには、食養の教えが根づきやすい土壌があったのです。
そんなベトナムでも、60年遅れで日本の公害のごとき現象が起きています。経済発展とともに、空気と水は汚れ、ベトナム中部の海では、日本の水俣病に似た病気で苦しむ人がいます。さらに問題を複雑にしているのが、日本以上に深刻な階級社会の問題。富める者は富み、貧するものは貧し、またコロナ禍で、人々の苦しみはさらに色濃くなっています。
私はこのような苦境を解決すべく、櫻澤先生の大切な教え、「正義の感覚」について人々に伝えたいのです。
食とは人を作る最も廣義の自然環境である。
養とは人がこの自然環境を攝取受用する正しき知行である。
即ち食とは自然の正義、養とは人間の正義、故に食養とは要する處人生の生を正しく遂ぐる事である。
(櫻澤如一著『食養学原論』より)
櫻澤先生が目指す食養とは、単に病気を直す手段ではなく、人間が生を正しく遂げるための方法です。そして、その正義の遂行は、自分だけで終わっては意味がない。すべての人が、生を正しく遂げられねばならないのです。
それが他人をも慮る、食養の基本なのです。今後も世界の人々が生を正しく全うできるように、櫻澤先生の教えを懸命に伝えていきたいと決意する次第です。



